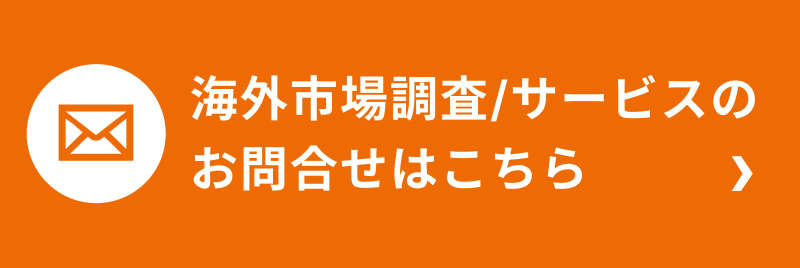【成功事例】日本・東南アジアのレンタルアパレル市場動向|サブスク型ファッションの成功と課題とは

はじめに
サステナブルファッションへの関心が高まる中、衣類の「所有」から「利用」へのシフトとして、サブスクリプション型ファッションレンタルが注目されている。特にアジアでは、環境意識の高まりやオンライン市場の拡大を背景にレンタル市場への潜在需要が存在する。海外では欧米中心に例が少なく、国内ではairClosetが創業10年で黒字化を達成するなど稀有な成功例も生まれている。以下、国内・東南アジアの代表的企業3社を取り上げ、ビジネスモデル・ターゲット、KPIや収益構造、成功要因・撤退要因、及び参入時の留意点について分析する。
各社の事業モデルとターゲット
airCloset(日本)
「airCloset」は女性向け普段着レンタルの先駆けであり、会員は月額7,800円からの定額料金でプロのスタイリストが選んだコーディネートセットをレンタルできる。予約制ではなく返却期限もないため、仕事で忙しい20~40代女性の需要を捉えている。累計で30,000人超の会員を抱え、成長を続けている。
利用後に気に入った服は会員向け特別価格で購入も可能で、小売チャネルとの相乗効果も享受している。販促費を抑えた長期的成長に注力し、継続課金からの累積データでサービスを磨く戦略が特徴である。同社はアジア市場への進出も視野に入れており、2024年にはベトナム・ハノイにシステム開発子会社を設立するなどグローバル展開を進めている。
Laxus(日本)
高級ブランドバッグのシェアリングサブスク「Laxus」。月額6,800円で任意の1点のハイブランドバッグを借りられ、返却後は別のバッグを借り替えできるシステムだ。登録アイテムはエルメス、ルイ・ヴィトン、シャネルなど約34,000点を超え、会員数20,000人以上(有料会員)を抱える。
また個人所有のバッグを貸し出す「LaxusX」も運営し、利用者と個人オーナー間の委託レンタルで市場を広げている。EC企業ワールドの子会社となり在庫調達力が強化され、バッグと洋服のコーデ提案など顧客体験の拡充が進む見込みだ。主にファッション感度の高い30~40代女性をターゲットに、国内で急成長している。
Style Theory(シンガポール・インドネシア)
東南アジア最大級だったデザイナーズ衣類・バッグのレンタルサブスク「Style Theory」。2016年創業後、ファッションレンタルアプリで一気に会員を拡大し、2019年には2.5億円(約2500万ドル)の資金調達を実施した。会員プランは月額S$89~S$149で、1回あたり数点(衣類3点+バッグ2点程度)を借り放題というモデルを提供していた。
2020年時点で登録ユーザー約20万人、レンタル実績1,000万点超(洗濯クリーニング・物流込み)と広範な在庫を抱え、シンガポール・インドネシア・香港へ展開していた。主に結婚式やパーティー用の高級ドレス・バッグを必要とする都市部の若年女性層を狙っていたが、2025年9月、運営コストの高騰や主要投資家の撤退を理由にサービスを終了し、東南アジアでは代表的な撤退事例となった。
成功要因と撤退要因の分析
レンタルアパレル市場においては、安定した成長を実現している企業が存在する一方で、市場環境への適応に苦しみ撤退を余儀なくされた事例もある。本節では、日本国内における成功事例であるairClosetおよびLaxusの取り組みを通じて成功要因を明らかにし、対照的に東南アジア市場で展開しながらも最終的にサービス終了に至ったStyle Theoryの撤退要因について検討する。
成功要因(airCloset・Laxus)
airClosetではパーソナルスタイリストによるコーディネート提案で付加価値の高いサービス体験を提供し、顧客ロイヤルティの向上に成功している。一方Laxusは、選りすぐりの高級ブランドと洗練されたアプリ体験を武器に富裕層の需要を掘り起こしている。両社とも解約抑制に注力しており、継続利用率は90%台以上と極めて高い水準を維持している。顧客データに基づく豊富な品揃えや適切なプロモーションにより、「欲しい商品が無い」「貸出中」といった顧客の離脱要因を潰す工夫を行っている点も特徴的である。

さらに、両社は独自の倉庫管理システム(WMS)や物流インフラを構築して運営コストの低減に努めると同時に、事業の多角化によって収益源を拡大している。具体的には、airClosetは「airCloset Mall」を通じてレンタルだけでなく購入機能を提供し、Laxusは「LaxusX」で個人間レンタルを可能にするなどプラットフォームビジネスを展開している。特にLaxusでは、リサイクル型ロジスティクスを構築し、自社プラットフォームを法人向けに貸し出す計画を示すなど、運用効率の改善に努めている点が成功要因となっている。
撤退要因(Style Theory)
Style Theoryではまず、衣類やバッグのクリーニング費用、輸送コスト、人件費などのコスト負担が拡大し、会員収益(ARPU)だけでは採算が取れない状況が続いていた。特に東南アジアでは物流インフラが未整備な地域も多く、返品・返却の手間や紛失リスクが大きいことがコスト増大をさらに悪化させた。また、事業成長には多額の先行投資(在庫調達やマーケティング)が必要で、資金調達に依存する構造であった。そのため主要投資家の撤退により運転資金の確保が困難となり、最終的に2025年末にサービスを終了せざるを得なくなった。
加えて、レンタル文化や競合環境の壁も大きな課題であった。東南アジアでは欧米ほどサブスクリプションやレンタルへの理解が進んでおらず、潜在顧客の嗜好変化にも時間を要していた。さらにコロナ禍で結婚式やパーティーなどの機会が激減したことで高級ドレスやバッグのレンタル需要が大幅に落ち込んだ。これらの要因が重なり、登録会員の離脱や新規会員獲得の頭打ちが発生し、事業継続が困難になったのである。
サステナブルファッション市場の伸び
世界的にファッション業界では「循環型経済(サーキュラーエコノミー)」への関心が高まっている。従来の大量生産・大量廃棄モデルから脱却し、二次流通やレンタル利用により廃棄削減を図る動きが強まっている。実際、ファッション市場で“買う”だけでなく“借りる”という選択肢が注目され始め、サステナブル志向の消費者層が増加している。サブスクリプションモデルは所有を減らし、アイテム寿命を延ばせるビジネス形態であり、今後も大きな成長が期待されるだろう。
海外進出時の留意点
海外展開では以下のリスクと対策を念頭に置く必要がある。
物流・配送体制
現地の配送インフラや住所体系を調査し、信頼できる物流パートナーを選定する。例えば東南アジアでは港湾税関や地方配送網に課題が多く、返品返却の管理コストが上昇しやすい。冷暖房管理不要とはいえ、梱包・洗濯の質維持に注意が必要である。
価格設定
現地の購買力と競合サービスを踏まえた価格戦略が不可欠。Style Theoryの月額S$89~149は富裕層向けだったが、中間層需要を取り込むには金額が高く感じられた側面もある。円・ドル以外の決済手段や現地通貨での課金、キャンペーン設定で柔軟に対応する。なお、アジアではクレジットカード浸透率が低いため、多様な決済手段(デジタルウォレット・コンビニ払い等)の整備が求められる。
商品紛失・破損リスク
貸出商品は消耗品であり、常に一定割合の汚損・紛失リスクがつきまとう。加入者には保証金や保険制度を用意し、返却されない場合の代償条項を契約で明示しておくべきである。Style Theoryの場合、閉鎖時には「保有中の衣類は当面保管、バッグは返却依頼」という異例の指示が発表された。これは未返却に備えた措置だが、顧客信頼を損なう要因にもなりうる。現地法規制・文化(レンタル品の所有権移転やコンプライアンス)も事前に確認する。
返品・クリーニング管理

衣類やバッグはクリーニング・検品コストが発生する。大量の往復輸送・検品作業が利益を圧迫しないよう、現地に倉庫・クリーニング拠点を設けるか、外部業者との提携を検討する。航空便と海運便の使い分け、リサイクル管理システム(RFIDタグ等)導入も検討課題である。
終わりに
以上を踏まえると、事業モデルの海外適用には現地特性の徹底理解が欠かせない。成功した日本企業も現地法人化・合弁展開・パートナー選定などで慎重に進出している。レンタルアパレルはまだ世界的にも成功例が少なく、ルールも未成熟な市場であるため、文化的嗜好や規制動向、競合環境を入念に調査することが成功への鍵となる。特に物流・マーケティング手法・価格帯の戦略性は国ごとに大きく異なるため、事前の実地調査で不確実性を削減し、自社の強みを活かしたサービス構築につなげることが重要である。レンタルアパレル参入を検討する企業は、今回の事例に学びつつ、海外市場で通用する独自戦略を練る足掛かりとしていただきたい。
情報参照先:
- 通販通信ECMO|エアークローゼット・天沼社長に聞く「サブスク成功の秘訣」とは?|(アクセス日:2025年10月20日)
- FiNE(通販マーケティング)|創業8年で売上34億円!airCloset急成長の裏側にある、“顧客体験”のつくり方|(アクセス日:2025年10月20日)
- パイロットボート|自宅のバッグを貸出し、定額で借りる。高級バッグのサブスクリプション「ラクサス」|(アクセス日:2025年10月20日)
- パイロットボート|〖Laxus〗SEQUEL:ワールドによる子会社化で向上する「ユーザ体験」|(アクセス日:2025年10月20日)
- PR TIMES(株式会社エアークローゼット プレスリリース)|エアークローゼットが自社開発した倉庫管理システム(WMS)の運用を開始|(アクセス日:2025年10月20日)
- PR TIMES(株式会社エアークローゼット プレスリリース)|『airCloset(エアークローゼット)』がサービス開始10周年を記念して、「特設サイト」やファッション市場・消費動向を読み解く「ファクトブック」を公開|(アクセス日:2025年10月20日)
- TechCrunch|Style Theory, a fashion rental startup in Southeast Asia, raises $15 million led by SoftBank Ventures Asia|(アクセス日:2025年10月20日)
- The Straits Times|Online clothes rental platform Style Theory shuts down; no refunds given to subscribers|(アクセス日:2025年10月20日)