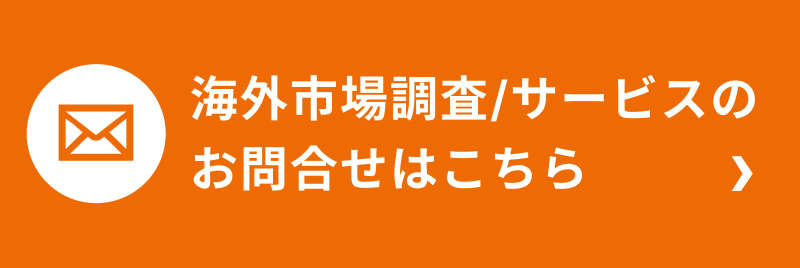【抹茶スイーツ市場最新動向】東南アジアで高まる抹茶人気|宇治抹茶の輸出拡大と価格高騰の背景

はじめに:東南アジアで拡大する抹茶スイーツ市場の人気
東南アジア各国において、近年日本発の抹茶スイーツが急速に人気を高めている。東南アジア地域(ASEAN)のカフェでは、抹茶ラテや抹茶フラペチーノといったドリンクが1杯4~6ドル程度で日常的に選択されるまでに普及しており、アイスクリームや焼き菓子など抹茶風味の加工食品も高い需要を獲得している。

特に東南アジアや中東地域における抹茶を使ったスイーツ・デザート向け市場は年間10%以上の成長率で拡大しており、抹茶の利用シーンが飲料以外にも広がっていることが分かる。 こうした抹茶人気の背景には、各国共通の健康志向ブームとSNS時代のトレンド、そして日本文化への関心がある。例えばシンガポールでは、国民の健康意識の高さやおしゃれなカフェ文化の浸透、日本の食文化への深い興味が重なり合い、抹茶ラテや抹茶スイーツが街中のカフェや商業施設で定番メニューとなっている。

さらに、日本の伝統文化への憧れも手伝い、「本物の抹茶」を求める消費者が増加している。実際、日本旅行で本場の抹茶を味わった人々が帰国後に現地で本格的な抹茶カフェに足を運ぶケースも増えており、「日本製」で品質管理の行き届いた抹茶ブランドへの信頼感が消費を下支えしている。
抹茶ブームがもたらす宇治抹茶需要の急拡大
世界的な抹茶ブームと東南アジアからの旺盛な需要の高まりは、高品質で知られる京都・宇治抹茶の供給状況にも大きな影響を与えている。
世界的需要の拡大と宇治抹茶の品薄化
京都府宇治市周辺で生産される宇治抹茶は約800年の歴史を持つブランド茶であり、その香り高さと旨味のバランスから国内外で「最高級抹茶」の代名詞となっている。

しかし、海外の抹茶ブームとコロナ後の訪日外国人急増を背景に、宇治抹茶は昨秋(2024年秋)頃から品薄状態に陥っている。京都府茶協同組合によれば、特にグレードの高い希少な抹茶への需要が急伸し、従来の生産量では供給が追いつかない事態となった。実際、令和5年(2023年)の日本の緑茶(抹茶を含む)輸出量は7,579トン、輸出額は292億円と過去最高を更新しており、この10年で輸出量は約2.5倍にも拡大した。その輸出額の7割超を抹茶など粉末茶が占めており、日本産抹茶に対する世界的需要がいかに急拡大しているかを裏付けている。 需要の急騰に伴い、国内の生産・流通現場では様々なひずみが生じている。
老舗茶舗の販売制限と高級抹茶争奪戦
宇治周辺の老舗茶舗や専門店では、個人で消費しきれない量の抹茶を爆買いする訪日客が確認されており、一時的に店頭販売を休止したり購入点数を制限したりする対応が取られ始めた。例えば創業300年の京都の老舗抹茶メーカー「丸久小山園」では、昨年10月についに一部抹茶パウダーが品切れとなり、長年取引のある茶道・寺社関係者への供給を優先するため一般向け販売に数量制限を設けざるを得なくなった。
同じく京都の老舗「一保堂茶舗」でも抹茶不足の影響で特定商品の販売を一時停止し、仕入れコスト上昇を受けて一部商品の値上げを実施している。さらに宇治茶の老舗「通圓(つうえん)」では、昨年11月頃から訪日外国人客が一度に10個以上もの抹茶商品を買い求めるケースが相次ぎ、一部の希少品が品薄となったため購入個数の制限を継続している。通圓の社長は「百貨店などでの抹茶購入制限の影響で当店に流れてきたのではないか」と述べており、業界全体で高級抹茶の争奪戦が起きている状況がうかがえる。
海外転売と高額取引の拡大
さらに深刻なのは、国内で供給不足となった宇治抹茶が海外の転売ヤーによって高額転売されている現象である。事実、東南アジア各国のオンラインショッピングサイト上で宇治抹茶が定価の2~3倍もの価格で販売されているケースが多数確認されている。
例えばタイのECサイトでは昨年末時点で、定価約1,500円(40グラム)の商品が約4,400円もの値を付けて売られていた。またベトナムやシンガポールのサイトでも、宇治の老舗茶舗の商品が定価の2倍以上の価格で取引されていたことが報告されている。こうした状況を受けて、日本国内の茶業者の中には転売目的での大量購入を禁止する旨を明示したり、同一住所への大量発送注文を拒否する対策を講じるところも出てきている。

京都府茶協同組合の担当者は「上級品はもともと数が少なく手間もかかっている。生産できる量には限りがある」と指摘し、当面は購入数量の制限などやむを得ない措置で対応するしかないと述べている。さらに「抹茶は長期保管すると品質が落ちるので、消費者には少しずつ必要な分だけ購入してほしい」と異例の呼びかけを行う事態となっている。つまり、日本国内でも伝統的な需要層である茶道関係者等への安定供給を維持しつつ、新規需要に対応するために需給調整が求められる逼迫状況となっているのである。
宇治抹茶供給の課題と今後の展望
宇治抹茶をはじめ日本産抹茶の供給現場では、現在いくつかの課題に直面している。
生産拡大の難しさと構造的制約
第一に、生産拡大の難しさが挙げられる。抹茶原料となる碾茶(てんちゃ)の栽培には最低でも数年単位の時間が必要であり、苗木を植えてすぐに生産量を増やせるものではない。

特に宇治抹茶は覆い下栽培や石臼挽きといった伝統的製法にこだわる面も多く、栽培・加工に手間と時間がかかるため急激な生産量拡大が困難である。加えて、生産農家の高齢化と後継者不足も深刻であり、需給ギャップが生じても国内生産体制を機動的に拡充できない構造的問題がある。
気候変動と価格高騰の影響
事実、近年の異常気象によって茶葉の収穫量が落ち込む事例もあり、京都・宇治市ではある茶農家が例年2トン収穫できていた碾茶を2023年には1.5トンしか確保できなかったとの報告もある。

このような生産量の減少と世界的需要拡大が重なった結果、碾茶の取引価格は高騰を続けており、2024年5月時点で碾茶価格は1キログラム当たり8,235円に達し前年同期比で大幅上昇したとみられる。こうした供給逼迫による価格上昇傾向は今後も続く可能性が高く、2025~2030年に世界の抹茶需要が年7%程度で伸び続けるベースラインシナリオでは、日本産原料の慢性的な不足によって毎年3~5%程度の仕入れ価格上昇が見込まれるとの予測もある。
政府・業界の取り組みと海外生産の台頭
この供給不足に対応すべく、日本政府や業界団体も動きを見せている。農林水産省は日本茶(抹茶を含む)輸出額の政府目標を2025年までに312億円と定めており、2023年に292億円と過去最高を記録した輸出額はその射程圏内に入った。こうした背景から抹茶の生産拡大と輸出促進が政策的にも掲げられており、例えば抹茶輸出向けのHACCP認証や有機JAS取得に対する補助金交付など品質保証体制の整備支援が行われている。政府や地方自治体、茶農家が協力し、スマート農業技術の導入や有機栽培への転換によって収量を増やす取り組みも模索されている。しかしながら、抹茶需要の伸びがそれ以上に急激であれば、生産拡大の追いつかない需給ギャップが当面残ることは避けられない。そうした中、海外産の抹茶が不足分を補完する動きも顕著になりつつある。

世界最大の緑茶生産国である中国では日本の供給逼迫を追い風に抹茶産業が急成長しており、特に貴州省銅仁市は「中国抹茶の都」を標榜して大規模投資を行っている。同市では2017年に世界最大級の抹茶加工工場が建設され、2023年には1,000トン超の抹茶を生産、そのうち400トン以上を海外に輸出したという。この生産量1,000トンという数字は日本全国の2023年抹茶生産量の約4分の1に相当する規模であり、中国がいかに積極的にこの市場に参入しているかが分かる。
さらに注目すべきは、2025年前半に銅仁市から初めて日本向けに4トンの抹茶が輸出され、今後追加で6トンの対日輸出が予定されている点である。品質面で一定の評価を得た中国産抹茶は、米国スターバックスや日本の外食大手ゼンショーホールディングス(牛丼チェーン等を展開)、中国の火鍋チェーン海底撈など国内外の大手企業の重要な調達先となり始めている。また、日本国内でも大手カフェチェーン各社が安定供給を最優先に調達先を絞り込む一方で、リスク分散策として中国産や韓国産の抹茶粉を補完的に導入する動きを見せている。いわば、日本産抹茶のブランド力と他国産抹茶の量的供給力とが併存する新たなサプライチェーンが形成されつつあると言えるだろう。
今後の展望と戦略的対応
将来的な展望としては、国内生産力の強化と需要の多角化の両面からバランスを取ることが鍵となる。生産面では、碾茶の機械化や品種改良、新規就農者の支援を通じた宇治抹茶産地の振興が求められている。需要面では、一部の専門家からは「抹茶一極集中」状態を緩和すべく、玉露・煎茶・焙じ茶といった他の日本茶にも海外の注目を向けさせることが提言されている。実際、日本産の紅茶や焙じ茶は健康志向の高い層に徐々に人気が出始めており、こうした代替品の海外プロモーションを強化することで抹茶需要の過熱を冷ましつつ総体としての日本茶輸出を拡大する戦略も考えられる。
いずれにせよ、東南アジアを中心に高まる抹茶スイーツ市場の勢いと、それを支える宇治抹茶の安定供給という二律背反をどう両立させるかが、日本茶業界にとって今後の重要な課題である。世界的な抹茶ブームは今後も継続すると見られるだけに、日本は質の高い抹茶ブランドを守りつつ市場の期待に応えるための持続可能な供給体制を模索していく必要があるであろう。
情報参照先:
- 抹茶タイムズ|【2025年最新版】抹茶市場の動向と将来性を徹底解説|国内外の市場規模・トレンド・事業参入のチャンス|(アクセス日:2025年9月24日)
- 抹茶タイムズ|シンガポールの抹茶事情|健康志向とカフェ文化が支える新しいブーム|(アクセス日:2025年9月24日)
- JAPAN Forward|海外から熱中視「宇治抹茶」売れ過ぎ 訪日客も爆買い、販売制限の動きも|(アクセス日:2025年9月24日)
- GLOBAL DAILY|世界的な抹茶人気で、日本では品薄状態。今後、お茶需要の分散化が鍵?|(アクセス日:2025年9月24日)
- note|なぜベトナムは今、抹茶に夢中なのか?データで読み解く|(アクセス日:2025年9月24日)
- 吉川真人の中国ビジネストレンド|日本抹茶不足で中国抹茶が躍進、貴州省銅仁市が「第二の宇治」を目指す|(アクセス日:2025年9月24日)